伊泉龍一 出版物詳細紹介
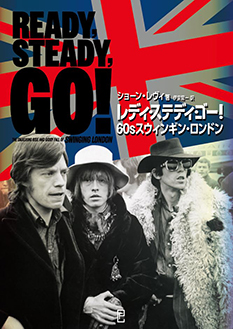
『レディ・ステディ・ゴー! 60sスウィンギン・ロンドン』
ショーン・レヴィ著 伊泉 龍一訳
¥5,280(税込)
60年代のロンドン。それは音楽、ファッション、アートの創造性が爆発し、それまで灰色だったイギリスの光景が一転して色鮮やかとなり、その旧態依然とした価値観や習慣が粉砕され、従来の階級社会の概念さえ麻痺させられるに至った「スウィンギン・ロンドン」と呼ばれる時代だった。
それはどのように始まり、どのように発展し、そしてその興奮と熱狂がいかにして世界中を席巻するに至ったのか?
本書の著者ショーン・レヴィは、ファッション、ヘアスタイル、ポピュラー・ミュージック、映画、写真、ファッション誌、テレビの音楽番組、アート・ギャラリー、レストラン、クラブ、ブティック、モデル、ドラッグなど多方面に目配りしながら当時の飛び抜けて面白い数々の逸話をつなぎ合わせ、その目もくらむような輝きに満ちた10年間の盛衰を見事に生き生きと描き出していく。
写真家デイヴィッド・ベイリーによってモデルのジーン・シュリンプトンが『ヴォーグ』誌の表紙を飾り、俳優のテレンス・スタンプが信じられないような夢を手に入れて成功に酔いしれる。
マリー・クワントが若い女性たちのファッションを一変させ、ヴィダル・サスーンの革新的なヘアカットがファッション・ショーの話題をさらい、ビートルズがポピュラー・ミュージックの概念を劇的に変化させる。
ロバート・フレイザーのギャラリーでの過激な展覧会やアンドリュー・オールダムによって演出された邪悪なローリング・ストーンズが保守派の大人たちを逆なでする。
カーナビ―・ストリートにはクールなファッションでめかし込んだモッドたちがあふれ出し、ザ・フーが「マイ・ジェネレーション」を過激に演奏する。
人気のテレビ番組『レディ・ステディ・ゴー』が若者たちの流行をリードし、大人気となったブティックのビバで安価な最新の衣服でおしゃれをした若い女性たちが街を闊歩する……。
本書は、そんなスウィンギン・ロンドンの華々しく舞い上がっていく始まりから急激に落下していく終焉までの状況が、その時代への哀惜とともに社会批評家の鋭くもアイロニカルなまなざしで眺められている。
20世紀のポピュラー・カルチャー史の中でもひときわ輝くスウィンギン・ロンドンの活気を今に伝えてくれる最良の一冊。
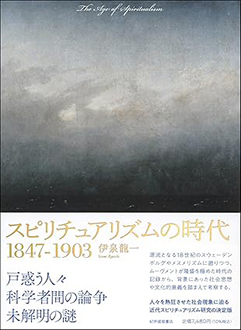
『スピリチュアリズムの時代 1847-1903』
伊泉龍一 (著)
¥7,480
人々を熱狂させた社会現象に迫る
近代スピリチュアリズム研究の決定版
19世紀半ばのアメリカに出現し、興隆を見せたスピリチュアル・ムーヴメントとはいったい何だったのか。ことの発端は1847年、ニューヨーク州の外れの小さな村で聞こえてきた不可解な音と、『自然の原理』という奇書の誕生だった。
「心霊主義」とも訳されるこのムーヴメントは、19世紀後半の英米圏で、産業革命がもたらした労働環境の悪化などに対する社会改革運動やキリスト教の退潮を後ろ盾に大きな流れになり、ウォレス、ダーウィン、ハクスリー、ファラデー、ティンダル、クルックス、シジウィック、ジェイムズ、パースら、第一線で活躍していた学者たちも巻き込んでいった。
源流となる18世紀のスウェーデンボルグやメスメリズムに遡りつつ、ムーヴメントが隆盛を極めた1847年から1903年までの資料から、“見えない力”や“霊的なるもの”に翻弄された人々の記録を辿りながら、その背景にあった社会思想や文化的意義を踏まえて考察する。
厖大な資料をもとにムーヴメントの興亡を克明に描き出した比類なき大著、待望の刊行!
【目次】
《第1部 スピリチュアリズムの台頭》
第1章 源流――メスメリズムからアンドルー・ジャクソン・デイヴィスまで
メスメルと動物磁気/ピュイゼギュールと磁気睡眠/メスメリズムの神秘主義化/アメリカに進出するメスメリズム/フレノメスメリズム/新たな啓示/アメリカのスウェーデンボルグ主義/医学的透視能力/啓示に至る四段階/超自然的なソースなのか?/霊的権威をめぐる問題
第2章 ムーヴメントのはじまり――フォックス姉妹による霊との交信
フォックス家から報告された不可解な騒音/交霊会のはじまり/リフォーマーたちに広まる霊との交信/公共の場での交霊会へ/ニューヨークのセレブリティとなったフォックス姉妹/ラップ音の調査とトリックの暴露/続々と現れるミディアムとムーヴメントの広がり/交霊会と女性の役割/食いちがう霊たちからのメッセージ
第3章 社会改革運動の夢――霊的テクノロジーから霊的社会主義のユートピアまで
フェルプス家での霊現象/霊の言語の解読/「電気」と「磁気」と霊現象/ミディアムになった博愛主義者/ヒーラーとしての目覚め/第三の時代を告げる預言者へ/電気の幼子/霊的社会主義のユートピア/スピリチュアリズムと社会改革/女性トランス・ミディアムと「女らしさ」の規範
第4章 エンターテインメント化する交霊会――霊のキャビネットから空中浮遊まで
クーンズ家の「霊の部屋」でのコンサート/ロープ抜け/霊のキャビネット/奇術疑惑/ミディアムと奇術師のあいだ/ペレット・リーディングとダーモグラフィー/ダニエル・ダングラス・ヒューム登場/事実を敬愛し名誉棄損を憎む/スラッジ氏/一八六〇年代アメリカン・インヴェイジョン/イギリス産スピリチュアリズムのはじまり
第5章 科学――霊の存在を証明しようとした科学者たち
メスメリズムからスピリチュアリズムへ/イギリスにおけるメスメリズムの広がり/テーブル・ターニングとオド/ヒプノティズムの誕生/テーブル・ターニングの原因/スピリットスコープ/科学的自然主義とXクラブ/科学者は交霊会で何を見たか/霊現象を認めたファラデー/科学と宗教の分断/霊界での適者進化の法則/ロンドン弁証法協会/何が可能で、何が不可能なのか/サイキック・フォースの発見/狼人間メスメリズム説/不朽の誠実さ/転向者たち/クルックスによる実験の結論/物質化し歩き回る霊
第6章 スター・ミディアムたちの光と影――全身物質化と劇場としての交霊会
モーゼスによる『霊の教え』/全身物質化のはじまり/ケイティ・キングはフローレンス・クックの偽装なのか?/人間の手で捕まえられた霊/写真におさめられた物質化した霊/クルックスの隠された想い/ダーウィンの不安/ダーウィン家での交霊会/ハクスリーが交霊会で見たもの/ミディアム VS ミディアム/物質化された霊の不気味な姿/全身物質化のトリック/「言語に絶するできごと」/光と影/英国心理学協会/クルックスとエリファス・レヴィ
第7章 変容するムーヴメント――スピリチュアリズムからオカルティズムへ
オカルティズムとエソテリシズム/エディ兄弟と全身物質化/懐疑派もゆらぐできごと/聖なる真実のための闘い/ケイティ・キングふたたび/全身物質化の暴露とそれへの反論/スピリチュアリズムのリーダーたちはスクールボーイにすぎない/ジョン・キングの自画像/オリエンタル・カバラ/神智学協会の設立へ/調和哲学
《第2部 サイキカル・リサーチ》
第8章 不可知論を超えて――マインド・リーディングからSPRの設立まで
スレート・ライティング/告発されたミディアム/四次元空間の証明/精神の直接作用と第六感/マインド・リーディング VS マッスル・リーディング/サイキカル・リサーチ協会の設立/シジウィックとキリスト教への懐疑/マイヤーズとスピリチュアリズムへの希望/SPR以前のシジウィック・グループ/不滅への願い/事実の上に事実を、実験に次ぐ実験を
第9章 サイキカル・リサーチのはじまり――テレパシーと生者の幻
テレパシーの誕生/テレパシー仮説/スレート・ライティング/SPRと神智学協会/人間の観察力と記憶の不完全さ/完璧な疑似交霊会/ガーニーと『生者の幻』/近代化された幽霊譚/その手紙はどこにあるのか/ジェイムズとASPRの設立/そもそも幽霊の調査は可能なのか/思考伝達実験への批判/『生者の幻』に対する批判/思考伝達実験での不正発覚/科学界の承認を勝ち取るために/ヒプノティズムとテレパシー/国際生理学的心理学会議
第10章 終焉――スピリチュアリズムを死に至らしめる一撃
第一級ミディアムの死/セイバート委員会/スピリチュアリズムを死に至らしめる打撃/ムーヴメントの終焉/交霊会を成功させるには/ジェイムズが衝撃を受けたミディアム/パイパー夫人の初期の交霊会/パイパー夫人を調査せよ/思考伝達だけで説明できるか/意識下の記憶/霊との間接的な交信/国際実験心理学会議と幻覚統計調査/撤回された詐欺の告白
第11章 白いカラスを求めて――レオノーラ・パイパーの謎
モーゼスの能力は本物だったか/私欲のない詐欺/リシェを確信させた物理ミディアム/パラディーノの実験/詐欺だとしても本物の能力がある?/わたし自身の白いカラスはパイパー夫人だ/最強のデバンカーの転向/それは死んだ友人の霊なのか?/生者とのテレパシーか、霊との交信か/『霊の教え』はまちがっていた?/懐疑派でも否定できない現象/新心理学 VS サイキカル・リサーチ
第12章 人間の人格と肉体の死後のその存続――フレデリック・マイヤーズと非宗教化された魂
シジウィックとマイヤーズの死/閾下自己/精神の進化/マイヤーズ問題
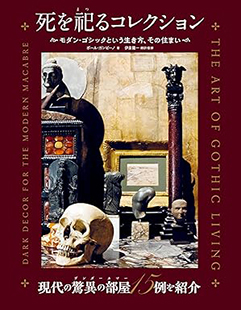
『死を祀るコレクション:モダン・ゴシックという生き方、その住まい』
ポール・ガンビーノ (著), 伊泉 龍一 (監修, 翻訳)
¥3,190(税込)
頭蓋骨、剥製から、人体模型や宗教的図像まで。 死を想起させる奇妙なものに魅せられた人々の住まい15例を、その家の住人たちのインタビューを交えて紹介。 ダークなマクシマリストたちの哲学を、その生活空間から解き明かす。
【目次】
序文/死の劇場/コーンズ夫妻によって選び抜かれたもの/家の元年/過去を取り戻す/
モダン・ゴシックの伯爵/家庭的な神秘主義/ゴシックの「霊」/アスモデウム ホール/
エンチャンテッド教会/心を落ち着かせるエナジー/1559年頃のボーン・ハウス/
オブスキューラの家/幽霊の出没にふさわしい屋敷/ゴシックのガリオン船/
アメリカ中西部のゴシック
【出版社からのコメント】
オハイオ州西部の霊に憑かれた教会、背筋が凍るような内部とは裏腹に、
おとぎ話のような外観のコネチカットのコテージ、驚異の部屋を彷彿とさせる内装の数々……。
本書では、15 軒の家の概略とその住人たちの人物像を描きながら、
ゴシック・サブカルチャーの信条に深く染み込んでいる哲学――個性、創造性、
人生の影の部分への魅惑――を反映させた、生活空間を創り出すまでの過程を詳しく紹介します。
既刊『死をめぐるコレクション』に続き、ポール・ガンビーノが、
魅惑的で美しくデザインされた暗黒の喜びに誘います。
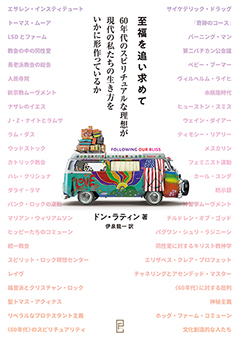
『至福を追い求めて ―60年代のスピリチュアルな理想が 現代の私たちの生き方をいかに形作っているか』
ドン・ラティン著 伊泉 龍一訳
¥4,180(税込)
至福を追い求めて ―60年代のスピリチュアルな理想が 現代の私たちの生き方をいかに形作っているか
六〇年代はアメリカの精神生活を一変させた。六〇年代は、その規模、その熱意、その純粋な創造性という点で前例のないほどの宗教的及びスピリチュアルな探求の爆発を引き起こした。『サンフランシスコ・クロニクル』紙の著名なジャーナリストのドン・ラティンが独特の洞察力とウィットと印象的な解説とともに、その並外れた時代のスピリチュアルな遺産の初めての包括的な調査を、その時代の最も突飛な実験の中心で育った人々の目を通して取り上げる。そして、ニューエイジの信念、フェミニストのスピリチュアリティ、東洋の諸宗教がどのようにして、そしてなぜアメリカの文化に、かくもしっかりと根を下ろしたのかを明らかにする。
このアメリカのスピリチュアリティの当時と現在を巡る刺激的な旅の中で、ラティンはアメリカの信仰の中核的な共同体――プロテスタント、カトリック、ユダヤ教――の中での劇的な変化はもちろんのこと、エサレン・インスティテュート、ハレ・クリシュナ、バグワン・シュリー・ラジニーシの教団、統一教会、ヒッピーのコミューンなどさまざまなスピリチュアルな共同体に生まれた子供たちに何が起こったのかについて、綿密な取材を基に詳述する。
その他にも、第二バチカン公会議、『魂のケア』の著者トーマス・ムーア、『奇跡のコース』とマリアン・ウィリアムソン、スピリット・ロック瞑想センター、仏教徒のパンクス、バーニング・マンとウィメンズ・テンプル、教会の中の同性愛、フリー・セックスを唱えるチルドレン・オブ・ゴッド、比較宗教学者ヒューストン・スミス、『ビー・ヒア・ナウ』の著者ラム・ダス、幻覚性ドラッグと宗教体験、福音派とクリスチャン・ロック、教会の中のドラッグとレイブ・パーティー、セルフヘルプのベストセラー著者ウェイン・ダイアー、チャネラーのJ・Z・ナイトと「ラムサ」、チャーチ・ユニヴァーサル・アンド・トライアンファントを率いた終末の預言者エリザベス・クレア・プロフェット等々、広範に及ぶ領域へと視野を広げながら、今日の宗教やスピリチュアリティの動向が、いかに六〇年代に始まった議論にそのルーツを持っているかを明らかにしていく。
【目次】
前書きと謝意
序 文
【第一部】〈六〇年代〉を探索する
第一章 エサレン・インスティテュートと〈六〇年代〉の最初の子供
第二章 神々の従者たち――希望を生き続ける
第三章 新たな啓示の中に奇跡を探して
【第二部】東洋へ向かって
第四章 ダーマ・キッズ―新たなアメリカの仏教徒の子供たち
第五章 ハレ・クリシュナにおける宗教的情熱と虐待
第六章 ラジニーシプラムに向かってうつむく
【第三部】セックスとドラッグとロックンロールと宗教
第七章 神とセックス―新しい道徳を探して
第八章 神とドラッグ―長く奇妙なトリップからの帰郷
第九章 神とロックンロール―保守的な福音主義者たちがエレクトリックへ進む
【第四部】失われた楽園
第十章 ムン牧師、救世主、そして次世代
第十一章 ニューエイジの預言者たちと暴利を貪る人たち
第十二章 コミューンとヒッピーの子供たち―ファームに嫌気が差して
結 論
原 注
訳者あとがき
索 引
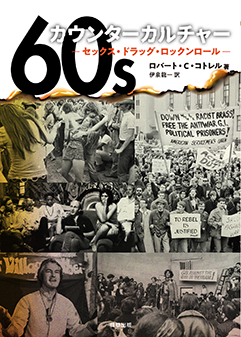
『60sカウンターカルチャー ~セックス・ドラッグ・ロックンロール』
ロバート・C・コトレル 著 伊泉 龍一 訳
¥6,930円(税込)
1960年代のアメリカ社会を激しく揺るがした「カウンターカルチャー」とは何だったのか?
その始まりから終焉までの流れを鮮やかに描き出しながら、その巨大なムーヴメントの実態を多角的な面から捉え直し、その全貌を改めて概観する。
・60年代のカウンターカルチャー以前のアメリカのボヘミアニズムやユートピア的な共同体主義。
・東洋のスピリチュアリティへと意識を向けたジャック・ケルアックやアレン・ギンズバーグらのビート・ジェネレーションからヘルマン・ヘッセのような文学者たち。
・オルダス・ハクスレーやティモシー・リアリーやラム・ダスやジョン・キージーのような精神探求や意識の拡張のためにドラッグを使用した先駆者たち。
・性の抑圧からの解放を訴えたヘルベルト・マルクーゼやノーマン・O・ブラウンやヴィルヘルム・ライヒの思想。
・各地で展開された反体制的なアンダーグラウンド出版。
・ディガーズによるフリー・フード・プログラムを中心とした反資本主義・反市場経済的な活動。
・行動主義心理学のB・F・スキナーのユートピア主義的な理想や各地に誕生した自給自足的なコミューンの状況。
・ヒッピーたちの記念すべき集会となったヘイト・アシュベリーでのヒューマン・ビーイン。
・ポピュラー・ミュージックの大規模な野外コンサートの原点となったウッドストック・フェスティバルやオルタモント・フェスティバルなど。
・サンフランシスコでの「サマー・オブ・ラブ」から「ヒッピーの死」まで。
・国防総省での行進を始めとする大規模な反戦運動。
・アビー・ホフマンやジェリー・ルービンなどを含むシカゴ・セブンの裁判。
・ブラックパンサー党やイッピーやウェザーメンなどの急進派の活動。
「60年代のそのムーヴメントは一瞬盛り上がって単に消えてしまった過去の特異な社会現象というよりも、その後の新たな世界へと向かっていく出発点だったと捉え直してみることもできるのではないだろうか」(訳者あとがきより)。
【目次】
序文
・第1章 先駆者たち― ユートピアからハクスリーへ
・第2章 新たなアメリカのボヘミアのための吟遊詩人たち― アレン・ギンズバーグやジャック・ケルアックなどのビートたち
・第3章 ビートの継続する受容
・第4章 ハーバード大学からミルブルックへ― ティモシー・リアリー
・第5章 メリー・プランクスター― ケン・キージー
・第6章 セックスという魔法の万能薬と無政府主義の影響
・第7章 音楽の中の魔法
・第8章 カリフォルニア・ドリーミングとヘイト・アシュベリー
・第9章 合図を広める― 代替メディア
・第10章 本を読む人々
・第11章 ヒューマン・ビーインからサマー・オブ・ラブまで
・第12章 ヒッピーの死と初期の事後論議
・第13章 別の生き方の可能性
・第14章 革命の途中でヒッピーがイッピーになる
・第15章 路上での戦いと諸集団の最後の闘争
・第16章 対敵諜報活動プログラムとミレニアム
・第17章 陰謀、街頭で戦う男、世の終末
・第18章 それほどスローだったわけではない衰退
・第19章 今やすべてが終わりに
・訳者あとがき
・参考文献
・索引
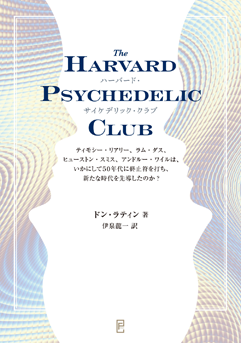
『ハーバード・サイケデリック・クラブ ―ティモシー・リアリー、ラム・ダス、ヒューストン・スミス、アンドルー・ワイルは、いかにして50年代に終止符を打ち、新たな時代を先導したのか?』
ドン・ラティン著 伊泉 龍一訳
¥3,850(税込)
カウンターカルチャーの始まりからニューエイジへ至るまで、時代を激変させた4人の交差する人生の物語。
LSDを通じての悟りの提唱者であるハーバード大学の心理学者ティモシー・リアリー。 世界の諸宗教についての専門家でMITの哲学教授ヒューストン・スミス。 インドを旅して求道者「ラム・ダス」となり帰ってきたハーバード大学の心理学者リチャード・アルパート。 ホリスティック・ヘルスと自然食品に関する提唱者となったハーバード大学医学大学院出身のアンドルー・ワイル。サイケデリック・ドラッグによる意識の拡大の後、彼ら全員が知性から直観、機械論的思考から神秘主義、学究的から精神的、科学的からシャーマン的な方向へと向かっていった。
そして、それぞれが独自の方法で、マインド/ボディ/スピリット運動の先駆者となり、ヨガ、菜食主義、東洋の神秘主義を西洋世界に広め、私たちの世界観に大きな変化をもたらすことになった。 この並外れた4人がハーバード大学でどのようにして出会ったのか、そして彼らのサイケデリック・ドラッグの研究プロジェクトでの実験が、いかにして本人たちの人生を激変させ、1960年代から1970年代にかけてのアメリカの文化を揺るがすことになったのか。本書において著者ドン・ラティンは、宗教ジャーナリストの視点からサイケデリックな60年代を改めて振り返り、そしてその意義を改めて問い直す。
【目次】
序文
第一章 ケンブリッジへの四つの道
第二章 ターン・オン
第三章 罪人たちと聖人たち
第四章 クリムゾン・タイド
第五章 楽園の中の悩みの種
第六章 もし君がサンフランシスコにやってくるなら……
第七章 巡礼と亡命
第八章 エクスタシーの後……四つの人生
結論 ヒーラー、ティーチャー、トリックスター、シーカー
後記
参考文献
原資料への注
『ハーバード・サイケデリック・クラブ』への称賛
謝辞
訳者あとがき
索引
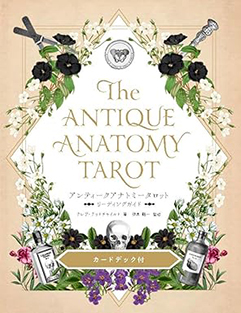
『アンティークアナトミータロット』
クレア・グッドチャイル著 伊泉龍一監修 みつじまちこ訳
¥4,180(税込)
アンティークアナトミータロット リーディングガイド
美しいカードデックと初心者にもわかりやすいリーディングガイドブックのセット。オカルティックな解剖学的イラストと繊細な植物イラストのコラボレーションで美しい箱入りセットでギフトにもおすすめ。
【目次】
はじめに/タロットの歴史/タロットの基礎/大アルカナと小アルカナ/数秘術とタロット/占星術とタロット/元素とタロット/色とタロット/タロットの使い方/デックの手入れ/スプレッド/カード・リーディング
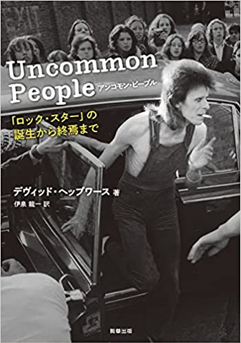
『アンコモン・ピープル ―「ロック・スター」の誕生から終焉まで』
デヴィッド・ヘップワース 著 伊泉 龍一 訳
¥4,950(税込)
1950年代半ばに「ロック・スター」は誕生し、1990年代半ばにこの世を去った。
私たちは彼らの中に何を見たのか? 私たちは彼らから何を求めていたのか?
テレビの普及、ドラッグの蔓延、エレクトリック・ギターへの注目、LP盤レコードの隆盛、CDの発売、MTVの始まり、ライブ・エイドでの世界的注目、スタジアムへと拡大してくライブ会場、大企業のCMとのタイアップ、音楽雑誌の隆盛、インターネットの到来……。こうした変化の中で生き続けてきた社会的・文化的な現象としての「ロック・スター」という観点から、各々の年を特徴づける逸話を追っていく中で、次第に一つの大きな物語としてのポピュラー・ミュージックの年代記が形作られていく。
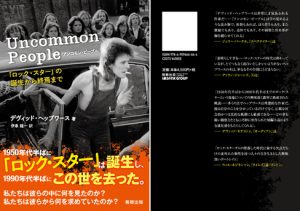
【目次】
序文
1955年9月14日 最初のロック・スター リトル・リチャード
1956年9月26日 最初のロック・アイドル エルヴィス・プレスリー
1957年7月6日 最初のロック・ファンたちがグループを始める クオリーメン
1958年5月22日 バッド・ボーイが飛んでくる ジェリー・リー・ルイス
1959年2月3日 グッド・ボーイが飛んでいく バディ・ホリー
1960年7月1日 ギター・ヒーロー参上 ハンク・マーヴィン
1961年9月25日 少年が自分自身を作り出す ロバート・ジマーマン
1962年9月28日 うまく入り込んだ男 リンゴ・スター
1963年5月1日 うまく入り込めなかった男 イアン・スチュワート
1964年12月23日 悲劇的な天才としてのロック・スター ブライアン・ウィルソン
1965年9月26日 進行中のドラマとしてのロック・バンド ザ・フー
1966年10月1日 街の新たな長官 ジミ・ヘンドリックス
1967年6月18日 最初の女性のロック・スター ジャニス・ジョプリン
1968年5月15日 オリュンポスからの眺め ポール・マッカートニー
1969年8月9日 悪魔の職分 ブラック・サバス
1970年6月24日 ロックの神がオカルトを抱擁する ジム・モリソン
1971年5月16日 再起 ルー・リード
1972年7月26日 ロックが上流社会へ向かう ローリング・ストーンズ
1973年7月3日 「ロック・スター」の引退 デヴィッド・ボウイ
1974年8月6日 複雑な世界の中でのロック ブルース・スプリングスティーン
1975年7月18日 最高のロックが常にロックであるとは限らない ボブ・マーリー
1976年7月4日 Ⅹファクター スティーヴィー・ニックス
1977年8月16日 死はビジネスにとって好ましい エルヴィス・プレスリー
1978年12月9日 チャートの頂点のラズベリー イアン・デューリー
1979年8月8日 神々の黄昏 レッド・ツェッペリン
1980年12月8日 ファンによる殺害 ジョン・レノン
1981年8月13日 セックス、暴力、テレビ デュラン・デュラン
1982年3月19日 巡業の炎上 オジー・オズボーン
1983年9月31日 ロック・スターたちのバカらしさ スパイナル・タップ
1984年1月27日 燃え上がるスーパースター マイケル・ジャクソン
1985年7月13日 ダンパーから聖人へ ボブ・ゲルドフ
1986年7月16日 間近にいるロックの王族 ボブ・ディラン
1987年8月1日 それらしく見える アクセル・ローズ
1988年9月9日 クローゼットを片づける エルトン・ジョン
1989年3月21日 浄化と節酒 ボニー・レイト
1990年5月29日 セレブとしてのロック・スター マドンナ
1991年11月24日 パーティーの終わり フレディ・マーキュリー
1992年5月7日 度を超す人間 レッド・ホット・チリ・ペッパーズ
1993年6月7日 経歴を自滅させる プリンス
1994年4月5日 最後のロック・スター カート・コバーン
1995年8月9日 オタクの逆襲 マーク・アンドリーセン
終幕
参考文献
写真許諾
謝辞
訳者あとがき
索引
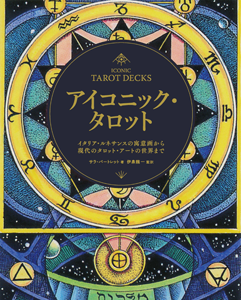
『アイコニック・タロット イタリア・ルネサンスの寓意画から現代のタロット・アートの世界まで』
サラ・バートレット 著 伊泉 龍一 監修・翻訳
¥2,970(税込)
タロットカードは、そのデザインも図柄も多種多様。 本書では、世界に無数に存在するタロットデックの中でも、特に美しい56種を紹介。 制作の背景、図柄に込められた思い、歴史の愛憎など、神秘と謎に包まれたタロットに迫る。
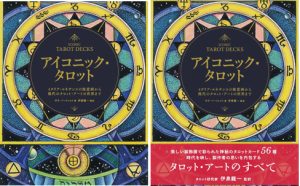
【目次】
本書を読む前に─監修者前書き─/序文/タロットの使い方/タロットの歴史/
第1章:影響力をもつデック/第2章:初心者のための占い用デック/
第3章:アートとしてのタロットとコレクターズアイテムとしてのタロット/
第4章:秘教的デックとオカルト・デック/第5章:現代のデック/終わりに/索引
【出版社からのコメント】
タロットカードは、基本的な構成はほぼ同じながら、カードに込められた意味、使用されているシンボル、
デザインなど、時代・地域・製作者によって、実に多種多様です。
本書は、タロットカードの歴史的変遷やその占い的使用法、意味などにも触れつつ、
そのアート性に焦点を当てて紹介しています。
占いや歴史的な側面を深堀りしたタロット本は数あれど、そのア―ト性、
シンボル・図柄の種類をここまで網羅したものはかつてなく、
そのバラエティの多さは一見の価値あり。
もっともポピュラーな『RWS(ライダー=ウェイト=スミス)』版から、
アレイスター・クロウリーらオカルトに傾倒したクリエイターによる神秘的なデック、
ダリの描いた自画像的デック、現代のCGを駆使して描かれたファンタジーデックなど、
美しく、興味深いタロット満載です。
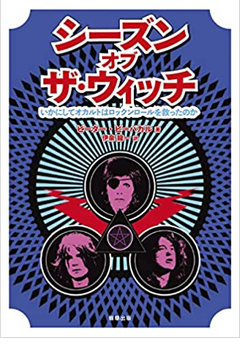
『シーズン・オブ・ザ・ウィッチ -いかにしてオカルトはロックンロールを救ったのか』
ピーター・ビーバガル 著 伊泉 龍一 訳
¥3,410(税込)
ロバート・ジョンソン、シド・バレット、ビートルズ、ドノヴァン、ローリング・ストーンズ、ブラック・サバス、レッド・ツェッペリン、アーサー・ブラウン、デヴィッド・ボウイ、サイキックTV、キリング・ジョーク、ホークウインド、キング・クリムゾン、イエス……。それらの背後で作動し続けたディオニュソス神話、ブードゥー、ヒンドゥー教、ロマン派、象徴派、カバラ、アレイスター・クロウリー、ブラバツキー夫人等々の宗教・神話・芸術・神秘思想に由来する「オカルトの想像力」を浮き彫りにする。
アフリカの宗教音楽からブルースへ。50年代のロックンロール。60年代のフォークソング、サイケデリック・ロック。70年代から80年代にかけてのハード・ロック、グラム・ロック、プログレッシブ・ロック、クラウト・ロック、エレクトロニック・ミュージック、ヘヴィ・メタル、インダストリアル・ロック、ポスト・パンク、ゴシック・ロック。さらには2000年代のドゥーム・メタルやストーナー・ロックまで。
「オカルト」を主軸としたポピュラー・ミュージックの斬新なナラティヴ・ヒストリー。
【目次】
序文 ウィー・アー・オール・イニシエイツ・ナウ
第1章 (ユー・メイク・ミー・ワナ)シャウト
第2章 リラックス・アンド・フロート・ダウンストリーム
第3章 ザ・デヴィル・ライズ・アウト
第4章 ザ・ツリー・オブ・ライフ
第5章 スペース・リチュアル
第6章 ゴールデーン・ドーン
参考・引用文献
謝辞
訳者あとがき
索引
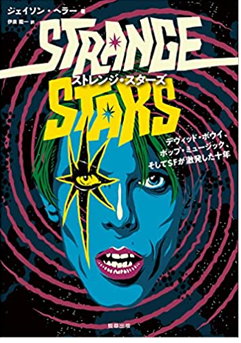
『ストレンジ・スターズ ―デヴィッド・ボウイ、ポップ・ミュージック、そしてSFが激発した十年』
ジェイソン・ヘラー 著 伊泉 龍一 訳
¥3,850(税込)
ヒューゴ賞受賞作家で音楽ジャーナリストの著者が、ポピュラー・ミュージック及びポピュラー・カルチャーへのサイエンス・フィクションからの大きな影響について風変わりで大胆なストーリーを踏査していく。
1960年代が終わりに近づき、古い慣習が、セックス、ドラッグ、ロックンロールで浮かれ騒ぐ新種の自由へと取って代われたとき、デヴィッド・ボウイは『2001年宇宙の旅』を見るため、ロンドンの映画館の空いている張り出し席に紛れ込んだ。そして、彼はすっかり別の姿になって現れてきた……。
そして実際にボウイは、人類が遠い世界に望遠鏡の照準を合わせたとき、かつて変人たちが好むくだらないものとして片づけられていたサイエンス・フィクションの世界を、60年代に始まった革命を継続するのに必要な促進剤としてみなすよう他のロック・スターたちを先導したのだ。
著者ジェイソン・ヘラーは『ストレンジ・スターズ』の中で、サイファイとポップ・ミュージックを、言葉、サウンド、この世ならざるイメージを使って創造可能なものの展望を拡張するために互いに頼り合っていた並行勢力として捉え直す。崇拝されているミュージシャンたちの一世代全体を、彼はサイファイに夢中になった魔法使いたちとして描き出していく。カリフォルニア大学バークリー校で宇宙の中の黒人について講義を行うサン・ラー、アポロ11号の月面着陸のBBCの番組で即興ライブを行うピンク・フロイド、「紫がかったか霞」を抽出するジミ・ヘンドリクス、『スターウォーズ』の波に乗ったディスコ・チャートのトップ、シンセサイザーを巧みに操るポストパンク……。
コミック・コンの熱狂者、スーパーヒーローの大ヒット作、古典的なサイファイのリブートといった今日のカルチャーによって、奇妙な趣味に打ち込む変人たちがついに勝利したとのだと私たちが考えてしまっているのだとしても、『ストレンジ・スターズ』は比類なき創造性――雑誌、小説、映画、レコード、コンサートの中での創造性――に満ちた時代を生き返らせ、すでにそうした変人たちがこれまでもずっと勝利し続けてきたのだということを明らかにする。
【目次】
序文
第1章 今日は星々がまるで違って見える―60年代の終わり
第2章 踊る高名な宇宙飛行士たち―1970年
第3章 イン・サーチ・オブ・スペース―1971年
第4章 俺はスペース・インベーダーだ―1972年
第5章 彗星のメロディー―1973年
第6章 電気回路の精神の神秘―1974年
第7章 お前たちのメモリーバンクは、
このファンクを忘れてしまっている―1975年
第8章 この見知らぬ装置に何ができるのか?―1976年
第9章 遠い惑星、そこから私はやってきている―1977年
第10章 宇宙のジャンクに激突される―1978年
第11章 機械がロックするとき―1979年
第12章 惑星は輝いている―80年代の始まり
原注
ディスコグラフィー
謝辞
訳者あとがき
索引
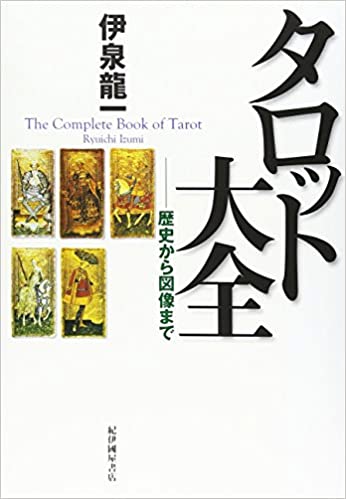

『エッセンシャル・ルノルマン ―的確で実践的な占いへのガイド』
ラナ・ジョージ 著 伊泉龍一、田中美和子 訳
¥3,850(税込)
21世紀のルノルマンの復興の原動力となった実践書の完全日本語訳。 アメリカを代表するルノルマン・カードの実践家が、長年にわたるリーディングの経験を基に、その技法と秘訣を徹底解説。 掲載カード:『ルノルマン・オラクル』
「ラナ・ジョージよりも優れた教師は見つけられない」―メアリー・K・グリア
各カードの意味、コンビネーションの解釈、スプレッド、リーディングの技法など、ルノルマンを実践する上で知りたいことのすべてを網羅。
ヨーロッパのルノルマンの伝統を踏襲しながらも、カード占いファン待望のタロットとルノルマンを組み合わせた画期的なリーディング方法まで紹介。
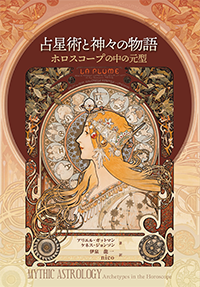
『占星術と神々の物語 ―ホロスコープの中の元型』
アリエル・ガットマン、ケネス・ジョンソン 著 伊泉 龍一、nico 訳
¥4,400(税込)
シュメール、バビロニア、ギリシャ、ローマ、インドなどを巡る古代の神々の物語12星座と惑星の元型的な意味を「神話」を通して理解する占星術の象徴を深く学んでいくための必読書!
C・G・ユング、エーリッヒ・ノイマン、マリー・ルイーゼ・フォン・フランツなどの心理学、ジョーゼフ・キャンベルやカール・ケレーニイの神話学、マリヤ・ギンブ タスの考古学、リーアン・アイスラーのフェミニズム論、デーン・ルディヤのヒューマニスティック占星術などを渉猟しながら書かれた「現代占星術」の金字塔です。

『生命の木-ゴールデン・ドーンの伝統の中のカバラ』
ジョン・マイケル・グリア著 伊泉龍一訳
¥4,400(税込)
「ゴールデン・ドーンの伝統」に基づくカバラを徹底解説した決定版的入門書。
生命の木の基本構造から10のスフィアーと22のパスの全ての象徴的意味に至るまで完全網羅。
占星術の星座・惑星、及びタロットの絵との関連から瞑想やパスワーキングの実践等も詳細に解説。
本書は1996年の初版以来、現代の儀式魔術の核心にあるカバラ魔術の哲学と象徴への入門の決定版として読み継がれてきました。
本書で解説されているのは、現代のカバラ魔術の中でも最も広く実践されているゴールデン・ドーンの伝統に基づくカバラです。
生命の木の全体的な構造、10のスフィアーと22のパスの全ての象徴的意味の詳細な解説ももちろんのこと、占星術の星座や惑星、タロットとの関係を始め、類書の中ではあまり触れられることのない要素までが網羅されています。
実践面では、初心者でも独学で始められる瞑想やパスワーキング等の方法も丁寧に解説されています。
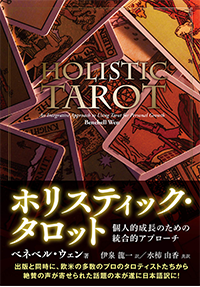
『ホリスティック・タロット―個人的成長のための統合的アプローチ 全2巻セット』
ベネベル・ウェン著 伊泉龍一訳 水柿由香共訳
¥8,580(税込)
出版と同時に、欧米の多数のプロのタロティストたちから絶賛の声が寄せられた話題の本が日本語訳に!
長年、タロットは「占い」のツールとして使われてきました。
それに対して、本書の著者ベネベル・ウェンは、 タロットを通して意識下の知識や創造性に触れていくための方法を提示しています。
それによってタロットは「未来を予言する」ことや「決められた運命を告げる」ためのものではなく、 今ここでの問題に向き合い個人の成長を促すためのツールにすること、それが本書のタロットへのアプローチです。
初心者にとっては、本書に含まれている包括的な情報と明解な説明が、 これからタロットの世界へ入っていくための最良のガイドとなるはずです。プロのタロット・リーダーにとっては、 500以上の図解とともに豊富なスプレッドと実践上の解釈例が、 より本格的なリーディングへステップアップするのに有益な指針となるでしょう。
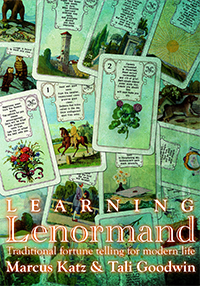
『ラーニング・ルノルマン』
マーカス・カッツ/タリ・グッドウィン著 伊泉龍一、七海くらら、田中美和子訳
¥3,300(税込)
あなたの感性と直観で読み解くルノルマン・カード占い。
タロット・カードよりもシンプルでフレキシブル。
英米で話題の『ラーニング・ルノルマン』が待望の日本語訳に!
近年日本でもルノルマン・カードを使った占いの人気が高まっています。
本書はルノルマン・カード占いに必要な情報を一冊にまとめた、海外で話題となっている解説書です。
一枚一枚のカードの意味、コンビネーションの読み方、「グラン・タブロー」と呼ばれる高度なスプレッドまで、段階を踏んで学ぶことができます。
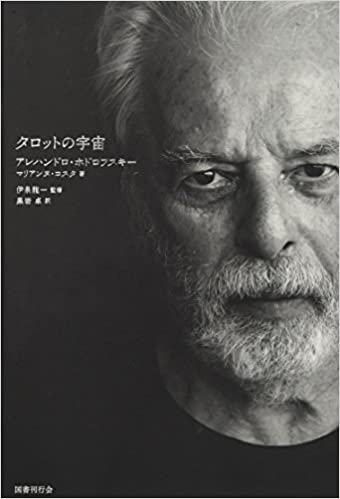

『シークレット・オブ・ザ・タロット――世界で最も有名なタロットの謎と真実』
マーカス・カッツ/タリ・グッドウィン著 伊泉龍一訳
¥3,850(税込)
なぜ「ワンドのクイーン」のカードに黒猫が描かれているのか? 「力」のカードに描かれている女性のモデルとなった人物は誰なのか? ウェイト=スミス・タロットを誕生させたふたりの作者が、その絵に込めた真の意図とは……。カードが出版された1909年のイギリスへと時代を遡り、秘められた真実をひもときます。
本書には類書にはない際立った特徴があります。それはカードの絵の解読のための鍵を探し、画家パメラ・コールマン・スミスの生涯へと光を当てていくというアプローチです。この試みは非常に新鮮な切り口となり、ウェイト=スミス・タロットに対する解釈の新たな地平の広がりを垣間見させてくれるものとなりました。ぜひ、日本のタロット・ファンに、そしてパメラの描いたウェイト=スミス・タロットの絵が好きで、その背景となっている世界にまで思いを馳せる方々に読んでいただきたい一冊です。
「シークレット・オブ・ザ・タロット」P118の下段に記載されている訳注「226」から「233」の番号表記に訂正があります。
正しくは「225」から「232」となります。
謹んでお詫び申し上げます。
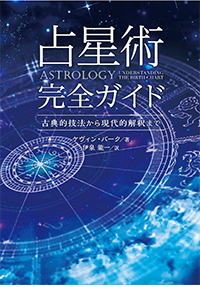
『占星術完全ガイド ――古典的技法から現代的解釈まで』
ケヴィン・バーグ著 伊泉龍一訳
¥3,300(税込)
初心者からプロまで、ホロスコープの解釈に必要な知識が、この一冊に凝縮。専門的な「アスペクト」の紹介、また多数のアスペクト・パターン、小惑星カイロン、月のノードなどについての詳細な解釈、そしてチャートの総合的な判断の手順などをこれまでの類書には見られないほど丁寧に解説。占星術を素早くかつ自信を持って実践したい人、必読の書。
<<フォールの欄の10段目の惑星の表記>>

その他、図の表現も含め、正しく修正した図を掲載した資料をご用意いたしました。下記のリンクよりダウンロードいただけます。
謹んでお詫び申し上げます。

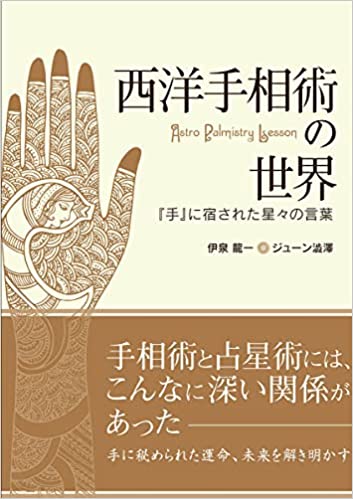
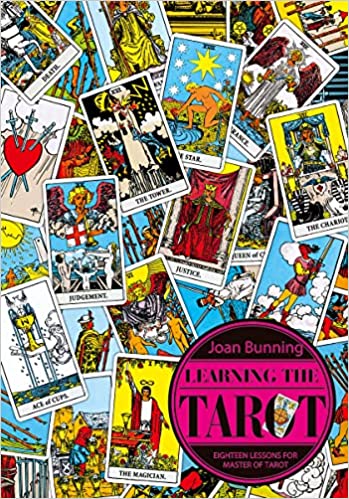

『数秘術の世界 -Modern Numerology Lesson あなたの人生を導く『数』の神秘-』
伊泉 龍一著 早田 みず紀著
¥2,640(税込)
第1部は「ヌメロロジーとは何か」から始まり、その人の「性格」・「才能」・「人生の目的」・「魂の求めるもの」などを数から導き出す具体的な方法とメッセージを、さらに、「未来予知」や「相性診断」に至るまで、あらゆるヌメロロジーについて紹介。(早田みず紀さん執筆) 第2部ではより本格的にヌメロロジーを勉強したい人のために、起源や歴史、さらに進んだヌメロロジーの理論などを詳しく説明。(伊泉龍一さん執筆) 初めての人から専門的に知りたい人まで満足できる現代数秘術の決定版!
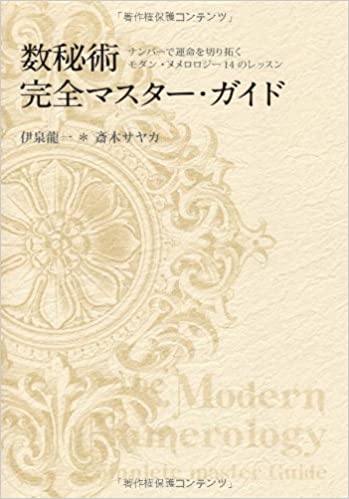
『数秘術完全マスターガイド -ナンバーで運命を切り拓く モダン・ヌメロロジー14のレッスン-』
伊泉 龍一著 斎木 サヤカ著
¥3,960(税込)
日本で初めて紹介されるナンバーを始め、数秘術のテクニックが満載。生年月日と名前から導かれる『数』があなたの可能性を開花させ、最大限の才能と魅力を引き出す。『数』の発しているメッセージに耳を傾けてください。
【出版社からのコメント】
本書は、2006年に発売された『数秘術の世界』(駒草出版)を導入のための書と位置づけるとすると、次の段階に進むための書といえる。生年月日と名前を使ってナンバーを導き出す基本テクニックは変わらないが、今回は自分の中の資質、魂、外面性、内面性に生ずる差異を徹底的に掘り下げることにより、潜在している自分の可能性を最大限に引き出すことができるものとなっている。また過去を振り返ることにより、未来への道しるべを明るく照らし出すことにも役立てることができるだろう。

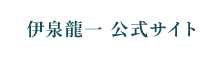
<<能動的大アルカナの左側>>
誤:陰 受動的エネルギー
正:陽 能動的エネルギー
正しく修正した図を掲載した資料をご用意いたしました。下記のリンクよりダウンロードいただけます。
PDF(修正資料)ダウンロード>>
謹んでお詫び申し上げます。